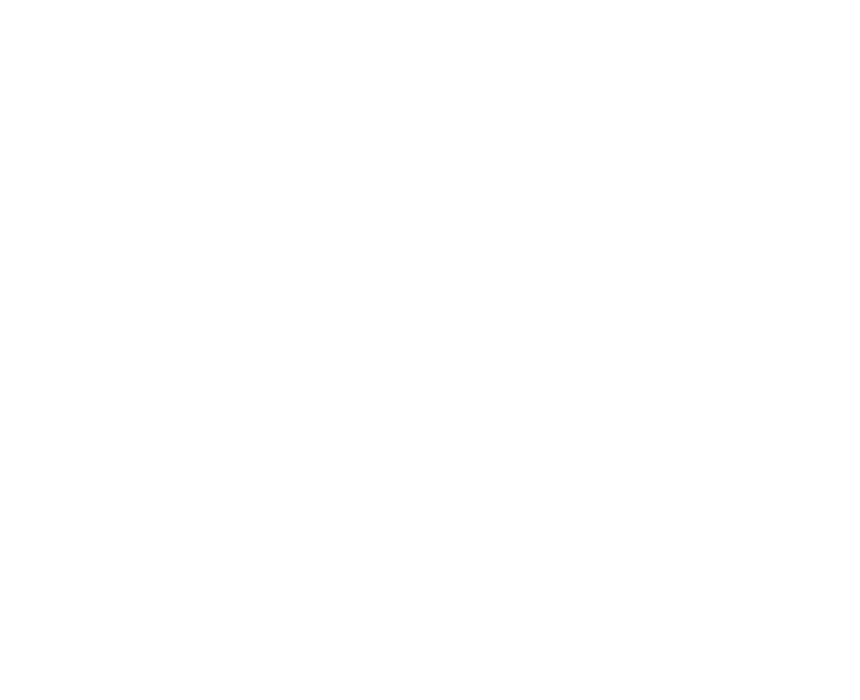産学連携サービス
EASE創研は、ソフトウェア工学に特化した産学連携サービスを提供いたします。
産学連携の歴史と背景
国内においては、主に1990年後半より産学連携への取り組みがなされ、近年の科学的な発見や革新的な技術を基盤とした社会背景を受け、産学双方における産学連携の更なる進化が必要な局面といえる。
産学連携の発展タイムライン
1990年代〜2000年代初頭
- 1998年 :大学等技術移転法(TLO法)施行
- 1999年 :産業活力再生特別措置法制定(日本版バイドール制度導入)
- 2003年:国による産学連携支援事業の開始
2010年代の産学連携の強化
イノベーション創出を阻害する隘路解消
- 知的財産戦略の推進:2014年に「知的財産基本法」が改正され、大学や研究機関の知的財産管理がより組織的に取り組まれる。
- 産学官連携の拡大:2015年には「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」が策定され、企業と大学の共同研究の枠組みが整備される。
- 大学発ベンチャーの支援:2016年以降、大学発ベンチャーの創出支援策が拡充され、スタートアップ企業との連携が活発化する。
2020年代の動向
社会課題や未来ニーズを起点とする価値創造
- オープンイノベーションの推進:企業と大学がより密接に連携し、共同研究の規模が拡大。国は大学への投資を増やす方針を決める。
- 研究資金の多様化:産学連携の資金調達手段が拡充され、民間資金の導入が進められました。
- 国際連携の強化:海外の研究機関と連携し、グローバルな共同研究が促進される。
産学連携の目的
産業界に於ける産学連携の目的
Society5.0などの急激な社会構造の変化において、日本の企業が革新領域での製品・サービスを持続的に社会実装するためには、企業に不足しがちな「高い基礎研究力」を有するアカデミアとのオープン・イノベーションを通じた多様性ある研究活動が重要になる。
アカデミアに於ける産学連携の目的
運営費交付金の大幅な削減を受け、大学等の運営基盤を強化するために、民間資金による資金多様化に取り組む必要がある。
このように、2010年以降の産学連携は、法的枠組みの整備と支援策の拡充によって、より戦略的かつ組織的に進化してきました。今後もさらなる発展が期待されます。
EASE創研の基本方針
当社の基本方針は、ソフトウェア工学分野(情報科学領域)に特化した産学連携(産業界と学術界の連携)の共創サービスを提供するものです。また、産学連携に基づくEASEエコシステム構築の目的と意義は、下記のとおりですが、その中核となる考え方は、社会課題の解決や持続可能な発展を目指し、異なる分野や組織間の知見・リソースを共有しながら、「幸せを実感できるイノベーション創出に貢献する」ことです。
目的
- 1.イノベーションの促進
大学や研究機関が持つ最先端の知見や技術を産業界に取り入れることで、新しい製品やサービスの開発を加速させます。
- 2.地域社会の活性化
地域の企業や大学が連携することで、地域資源を活用し、地元経済や雇用の創出に貢献します。
- 3.競争力の強化
グローバルな市場での競争力を高めるため、大学の研究成果を産業界のニーズに合致させ、実用化を進める基盤を作ります。
- 4.人材育成
学生や研究者が実際の産業界での経験を積むことで、現場で活躍できる実践的な能力を持つ人材を育成します。
意義
- 1.知見の循環
研究機関から生み出される知見が産業界で応用されるだけでなく、そのフィードバックによって新たな研究課題が生まれることで、知見の好循環を実現します。
- 2.持続可能な発展
環境、エネルギー、医療、ITなど多様な分野で課題を解決し、持続可能な社会を目指す取り組みに寄与します。
- 3.多様性の促進
異なるバックグラウンドを持つ人々や組織の交流により、新しい視点や価値観を取り入れた柔軟な発想を生む土壌を構築します。
産業界と学術界が協力することで、従来では成し得なかった課題解決や価値創造を可能にし、新たな時代を切り開く基盤としての役割を果たします。
EASEエコシステム

産学連携サービスメニュー
共同研究
大学や研究機関と企業が協力して、新しい技術や製品の開発、生産性向上などを目指すことです。大学や研究機関が持つ技術や知見を企業が活用することで、新しい製品やサービスの開発につなげることができます。また、企業側から大学に対して、研究テーマの提供や研究費の支援などを行うこともあります。
研究契約
大学や研究機関と企業が共同で研究を行うために結ぶ契約のことです。研究テーマや期間、費用などが明確に定められ、双方が合意した内容に基づいて研究が進められます。また、研究成果の知的財産権についても契約で取り決めることがあります。
知財共有
研究成果の知的財産権については、契約で取り決めることが一般的です。例えば、大学や研究機関が開発した技術や発明について、企業が独占的な使用権を得る代わりに、ライセンス料を支払うことがあります。また、逆に企業側が開発した技術や発明について、大学や研究機関が独占的な使用権を得ることもあります。
人材交流
大学や研究機関の研究者が企業に出向いて、企業の研究開発に参加することで、新しい知見を得たり、実践的なスキルを身につけたりすることができます。また、逆に企業側の研究者が大学や研究機関に出向いて、最新の研究成果を取り入れたり、新しい技術や知見を習得したりすることもあります。
セミナー・講演会
大学や研究機関の研究者が、自身の研究成果や知見を企業側に紹介することで、企業側が新しい技術や知見を得ることができます。また、逆に企業側が自社の技術や製品について、大学や研究機関の研究者に紹介することで、新しいアイデアや視点を得ることができます。