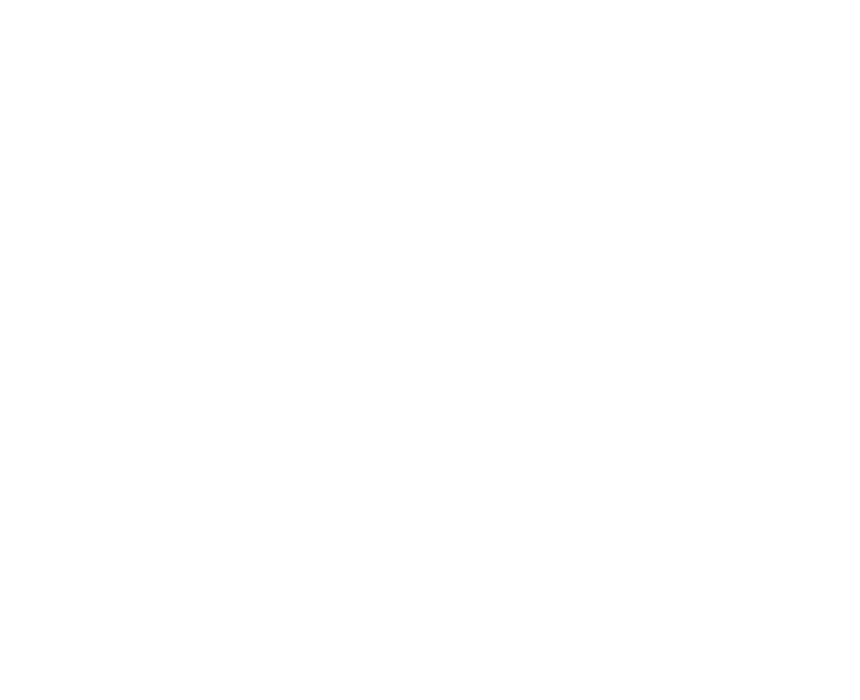研究テーマ&研究者ネットワーク
EASE創研が取り組む主要な研究テーマと研究者ネットワークについてご紹介します。
当社の産学連携ビジネスは、文科省・経産省「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン【追補版】」及びこれまでの大学等の改革や産学官連携に関わるポリシーを踏まえたアカデミアの参画に取り組んでいます。実際の活動としては、大学等の兼業・クロスアポイントメント制度に即した産学連携ビジネスの活動となります。
(2018年1月 厚労省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」)
兼業は、迅速な措置が可能であるという利点を活かし、組織的な人材交流に向けた移行期・試行段階の対応や、短期間のプロジェクトでの機動的な対応に活用することなどが考えられる。組織としての関与の在り方が明確なクロスアポイント制度は、民間企業との産学官連携活動により本格的に時間を割いて取り組むことのできるため、組織的な連携を展開していく上で有効な手段のひとつであると考えられる。
何故、産学連携ビジネス領域が"ソフトウェア工学"なのか?
そして、産学連携領域としての"ソフトウェア工学"の将来性と成長性は、どうなのか?
ソフトウェア工学は、今後も急速に成長し続ける分野です。その将来性と成長性について、以下のポイントで説明します。
ソフトウェア工学の将来性
デジタルトランスフォーメーションの推進
あらゆる業界でデジタル化が進んでおり、ソフトウェア工学の技術は企業の競争力向上に欠かせない。
AI・クラウド技術の発展
AIやクラウドコンピューティングの進化に伴い、ソフトウェア開発の需要がますます拡大しています。
IoT・自動化の拡張
製造業や物流など、多くの産業でIoTや自動化技術が導入され、ソフトウェア工学の重要性が高まっています。
セキュリティとプライバシーの強化
サイバーセキュリティ分野では、新たな脅威に対応するためのソフトウェア開発が求められています。
ソフトウェア工学の成長性
市場規模の拡大
近年、ソフトウェア産業は急成長しており、特にクラウドサービスやSaaS(Software as a Service)の分野での市場拡大が顕著です。
投資の増加
世界中でテクノロジー企業への投資が加速し、スタートアップから大企業までソフトウェア開発に積極的に投資しています。
人材の需要増
ソフトウェアエンジニアの需要は今後も増え続け、プログラミングスキルを持つ人材の価値が高まっています。
ソフトウェア工学の魅力
産学連携のビジネスモデルを考える上で、これらの成長性を活かした戦略を立てることで、より成功しやすくなります。
ソフトウェア工学は産学連携において非常に魅力的な分野です。その理由として、以下の点が挙げられます。
イノベーションの推進
大学の研究機関では最新のアルゴリズムや技術を開発し、それを企業が実用化することで、革新的なソリューションを生み出すことができます。
人材育成と技術の応用
学生は企業との共同プロジェクトを通じて、現実の課題に取り組むことで実践的なスキルを習得し、企業側は優秀な人材を確保しやすくなります。
スピーディーな技術発展
ソフトウェア技術は短期間で進化するため、産学連携を活用することで、新技術の市場導入を加速できます。
コスト効率の向上
企業は大学の研究成果を活用することで、高額な研究開発費を抑えつつ、高品質な技術を導入できます。