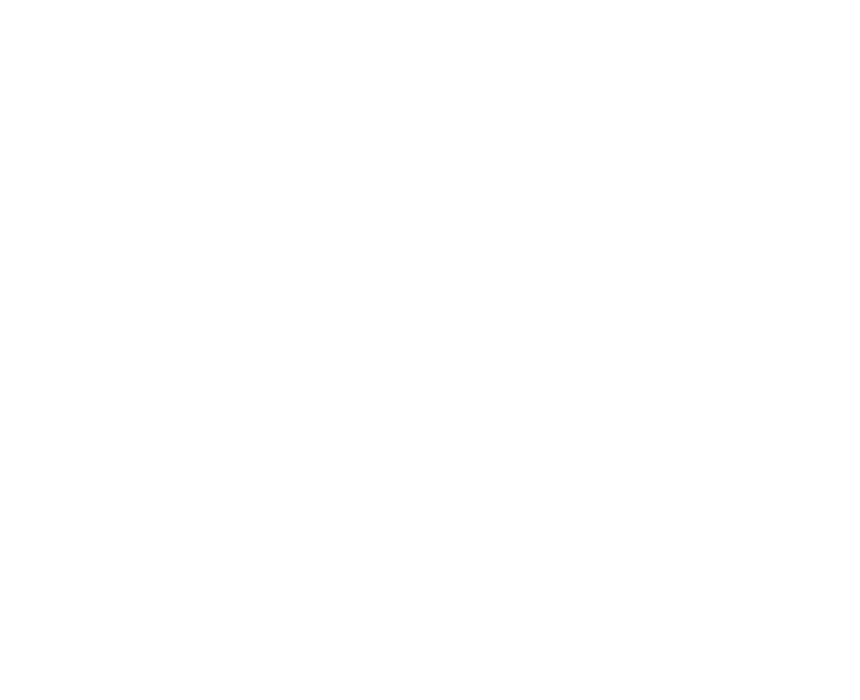株式会社EASE創研は2008年に合同会社として大学の仲間で立ち上げたベンチャー企業である。
大学の色々な成果は担当学生の卒業や研究グループの解散とともに論文を書いて消えていく運命にある。
この現実に対して、企業の力を借りて大学人が継続して社会に貢献し、人を幸せにしたいとの夢をもって発足した会社である。
その狙いは、ソフトウェアに関して「産学連携」を実現する場の設定であった。「大学の研究成果や技術力の移転」を標榜した。
しかし、研究成果とは論文としてまとまった結果が主で、研究成果から企業で商品化されるまでの道のりには、いわゆる「死の谷」と称される苦しい過程があり、そこから這い上がる力がない状態が続いたともいえる。
なお、産学連携の実現は一筋縄では実現できなくて、一つの研究テーマくらいのむつかしさがある。
詳細はホームページの内容としてご覧いただきたい。
合同会社EASE創研は2019年までなんとかつぶれずに継続し、2019年に企業出身者の参加を得ることができ、2022年に株式会社として模様替えをした。
我が社はソフトウェア工学という筋を通している。中でも、「エンピリカル」なアプローチである。
因みに、エンピリカルとは経験や実験などを通じてデータ重視の実践的な考え方である。
ソフトウェア工学という言葉は1968年以来存在していることは周知の通りだが、最近の「生成AI」の出現によりソフトウェア工学も様変わりしつつある。
当初はソフトウェアの基本はプログラミングとの考えで教育現場は学生を育ててきたが、生成AIの出現で極論としてプログラミング教育不要論があるとも聞く。
また、ソフトウェア工学はシステム工学であるとの議論も1990年頃から活発であり、最近では技術力というよりも人間力と呼ばれるような高邁とでもいうべき力が必要であり、今後の変遷に期待がふくらむ。
ソフトウェア工学と言われてからもうすぐ60年経過し、人間でいえば還暦を迎えることになる。還暦で定年を迎えると、人間ではそのあとに喜寿とか米寿とか、お祝いの対象にする年次が刻まれる。
今まさに、生成AIの出現でソフトウェア工学は還暦として生まれ変わり、今後の成長を期待されている。
そこには、従来のデータにもとづくエンピリカルな思考が底流にあって、最近のデータサイエンスやLLM(大規模言語モデル)など膨大なデータを利用して成り立つ世界があることを思えば、データ思考のエンピリカルから現代の生成AIに繋がってくる。
友人のVictor Basilは1984年以来エンピリカルな流れを具体化して、GQM(Goal Question Metrics)を初めとして、代表的なモデルを次々と提案してIEEEのソフトウェア論文誌から1980年代の10年間での優秀論文として位置付けられている。
今、エンピリカルを生成AIに置きかえてみると、ソフトウェアの今後を占うヒントになるかもしれない。しかも、現実のナマのデータは企業にあるが、使えるデータにした上で、使う技術力はどちらかと言えば大学側にあるので、産学連携への期待が大きい。
改装なったEASE創研はその中心にあり得たいとの想いで日夜励む毎日であり、産も学も真の仲間になる日を実現したいと願っている。
―以上―